こんにちは、現役国立医学部生のたくみです
大学への数学スタンダード演習って?実際どうなの?
という疑問に答えていきます。
僕が大学への数学シリーズの中で一番愛用していたので
大学への数学の中での立ち位置や特徴を知りたい!
という人はぜひ最後まで見てみてください。
大学への数学スタンダード演習とは
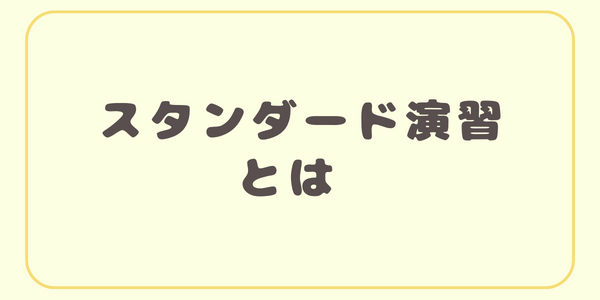
大学への数学シリーズには1対1対応の数学、新数学演習、そしてスタンダード演習とありますが、スタンダード演習は3冊の中で平均的な難易度の問題集です。
平均的といっても大学への数学シリーズなので難易度は高めに設定されています。
他の出版社と比較すると”やさしい理系数学”ぐらいです。
・【数学を得点源に!】やさしい理系数学のレベルや特徴を解説!

スタンダードって書いてあるけど難しめの問題集です。
大学への数学スタンダード演習は、ⅠA・ⅡBとⅢの2冊があり、毎年4月と5月に増刊として発行されます。
毎年入試問題を研究して改良されているので良問が多いです。
大学への数学スタンダード演習のメリット
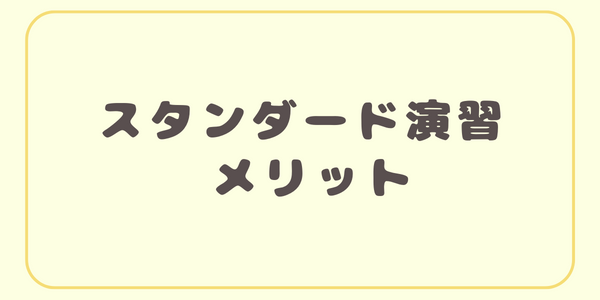
大学への数学スタンダード演習は良問ぞろいで解説が秀逸でいうことがない問題集です。
青チャートなどの網羅系参考書を取り組めばある程度の入試問題は解けるようになりますが、圧倒的な数学力をつけることができません。
それは、
数学の本質を理解しきれていない
からです。
網羅系参考書は解法を覚えて、解法の使い方を学ぶことに焦点が当てられています。
大学入試の数学はで対応できますが、1部の最難関大学や数学を得点源にしたい人からすると少し寂しいです。
一方、スタンダード演習は解説が秀逸です。
基本的な公式や定理から問題を解きほぐしているので数学の本質を理解することができ、応用力が劇的に向上します。

僕は、1部のほとんどの入試のの数学で7割以上解けるようになりました。
大学への数学スタンダード演習のデメリット
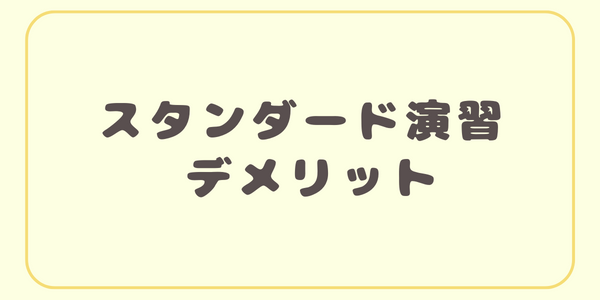
スタンダード演習は、基礎が盤石な状態で取り組まないと意味がありません。
解説が簡潔なので数学力がある程度ないと途中で挫折してしまう可能性が高いです。
青チャートが完璧じゃない、、、
という人は網羅系参考書を優先的に取り組みましょう。
・【青チャート】のレベルは?基礎問題精講との比較も!特徴と使い方を解説!
大学への数学スタンダード演習の取り組み方
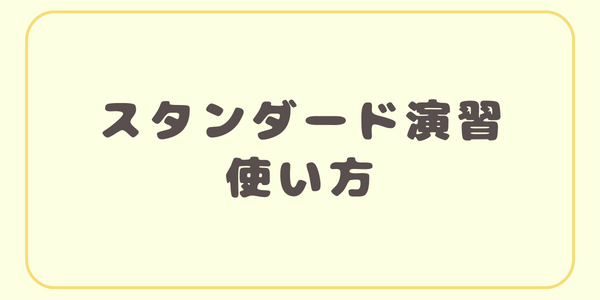
スタンダード演習のやり方は2つあります。
すべての問題に取り組む
頻出単元だけ取り組む
すべての問題に取り組む
数学を得点源にしたい!
という人は全問題に取り組みましょう。
全問題に取り組むと単元ごと繋がりが理解できるようになります。
頻出単元だけ取り組む
応用力をつけたいけど、あまり時間がない、、、
という人は頻出単元だけ取り組みましょう。
大学によって頻出単元は違うので志望校の過去問を研究してから取り組むのもよい方法だと思います。
大学への数学スタンダード演習に関するよくある質問
独学で進めることができる?→可能だが、、、
A:独学で進めることは可能です
大学への数学シリーズは、実践力が身につく優秀な教材ですが、解説が簡潔なので独学で進めることができる人は限られていると思います
独学で進めるのが不安な人は、受験数学のプロと一緒に進めてみましょう
今、全国の受験生の間で話題の【メガスタ】は、
オンライン家庭教師でありながら、「94%以上が届いていない状況から逆転合格」という実績を持っています。
📦 無料資料でわかること:
- 難関大・有名講師による指導内容
- 成績を上げるための具体的な学習戦略
- 実際に合格した生徒の体験談
- 自宅で受けられる授業スタイルの詳細
【今すぐ無料で資料をもらう】
1対1のオンライン家庭教師なら【メガスタ】大学への数学スタンダード演習のまとめ
今回は、スタンダード演習のレベルや特徴をお話ししました。
最後に参考書適性診断です。
数学を得点源にしたい!
青チャートなどで受験数学の基礎を完璧にした!
という人はぜひ取り組んでみてください。
数学の基礎力がついた状態で取り組むと殻が破れて飛躍的に成績が向上します。
個人的にとてもお勧めなので使ってもらえると嬉しいです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!


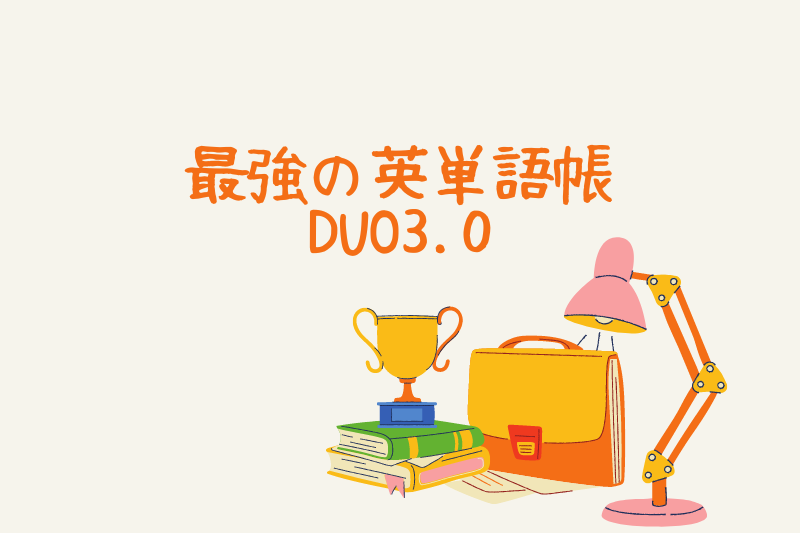
コメント