こんにちは、現役国立医学部生のたくみです
今回は
赤チャートのレベル感や特徴、使い方
を解説していきます。
赤チャートは難しすぎるといわれていますが、真相を明らかにしているので
赤チャートを使うか迷っている、、、
人はぜひ最後まで見てみてください
「赤チャート」の特徴?

「赤チャート」は、受験数学における王道ともいえる『チャート式』シリーズの一つ。シリーズの中で、特に難関大学を目指す受験生向けに作られたのが、この「赤チャート」です。その特徴的なカバーの色から、自然と「赤チャート」と呼ばれるようになりました。
「赤チャート」は、標準レベルから難関大レベルまでの幅広い問題が収録されています。特に、偏差値60以上の大学を志望する受験生にとっては、必須とも言える一冊です。全ての問題に対して詳細な解説があり、丁寧なステップバイステップの説明が数学の概念をより深く理解する手助けとなります。
赤チャートのレベル
赤チャートに挑戦できる人のレベルは全統記述模試で偏差値70
赤チャートに取り組むとすべての大学で数学が合格点に到達する
赤チャートが必要ないといわれる理由
赤チャートが必要ないといわれる最も大きな理由の一つは難易度のわりに問題数が多すぎることです。
基本的に大学受験数学の流れは、①教科書レベルを抑える②基本の解法を覚える③応用問題に取り組むの3ステップから成り立っています。
赤チャートは③の応用問題に取り組む時期に該当しますが、多くの人は①や②に時間がかかるので③にかける時間が残されていません。
なので、赤チャートを最後までやりきれない可能性が高いためおすすめされないです。
「赤チャート」を使い方と注意点
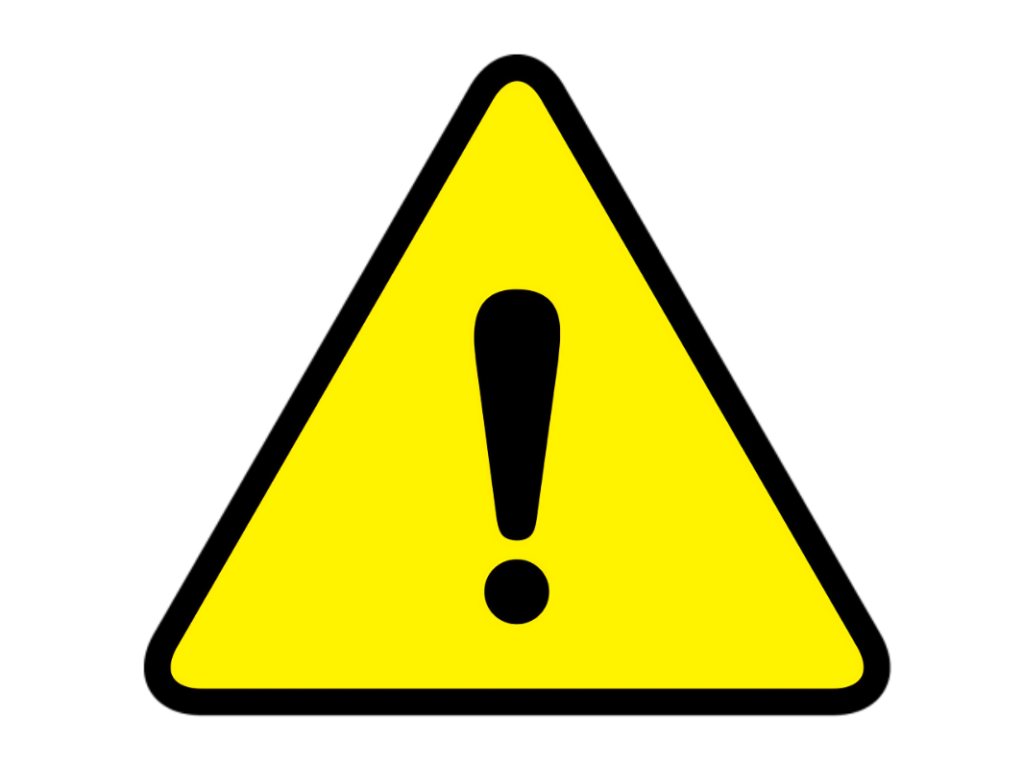
解法暗記に頼らない
解説を読むときは、単に「こう解くのか」と思うだけでなく、「なぜその解法が有効なのか?」を自問自答しながら進めましょう。問題を解くためのロジックや着眼点を理解することで、類似の問題にも対応できるようになります。
特に赤チャートは応用期の参考書に該当するので基礎の解法をどのように使っていくかという視点を大事にしてほしいです。応用問題は基本的な解放の組み合わせで作られているので、解法期に学んだ解法がどのように使われているかを意識しながら進めましょう
全ての問題を解く必要はない
「赤チャート」はとにかく問題数が多く、すべて解くのは現実的ではありません。自分の志望校に合わせて、特に必要な分野や問題に重点を置いて取り組むことが大切です。
定期的な復習を忘れずに
難しい問題ほど、時間が経つと解法を忘れてしまいます。解けなかった問題や重要な問題には印をつけ、定期的に復習することで、確実に得点源にしていきましょう。

僕は、1日後、1週間後、1か月後に解きなおしていました
最後に
「赤チャート」は、難関大学を目指す受験生にとって、信頼できるパートナーとなる参考書です。偏差値や志望校に応じて効率的に活用し、ぜひ受験数学を制覇してください。あなたの努力が必ず報われますように!
独学に不安を感じている人へ
「問題集だけだと、わからないところを解決できない…」
「スケジュール管理が難しい…」
そんな悩みを抱えている受験生も多いのではないでしょうか?
そんなときは、現役東大生が個別指導をしてくれるオンライン塾『トウコベ』の活用を検討してみてください。
世の中に学習塾はたくさんありますが、正直、自己満足のために教えている先生が一定数いることも確かです。
東大生は、勉強の経験値が違うので生徒に合わせた勉強方法を伝えることができたり、東大という高い壁に上ったからこそわかるモチベーションを維持する方法を親身になってサポートできたりします。
トウコベなら、
- あなたの弱点に合わせた完全個別カリキュラム
- 自学型学習とプロの指導を両立
- 自宅にいながら高品質な指導を受けられる
という圧倒的なサポート体制で、独学の不安を解消できます。
✅ 詳細はこちら ↓
トウコベ公式サイト受験勉強に不安を感じたら、ぜひ一度チェックしてみてください
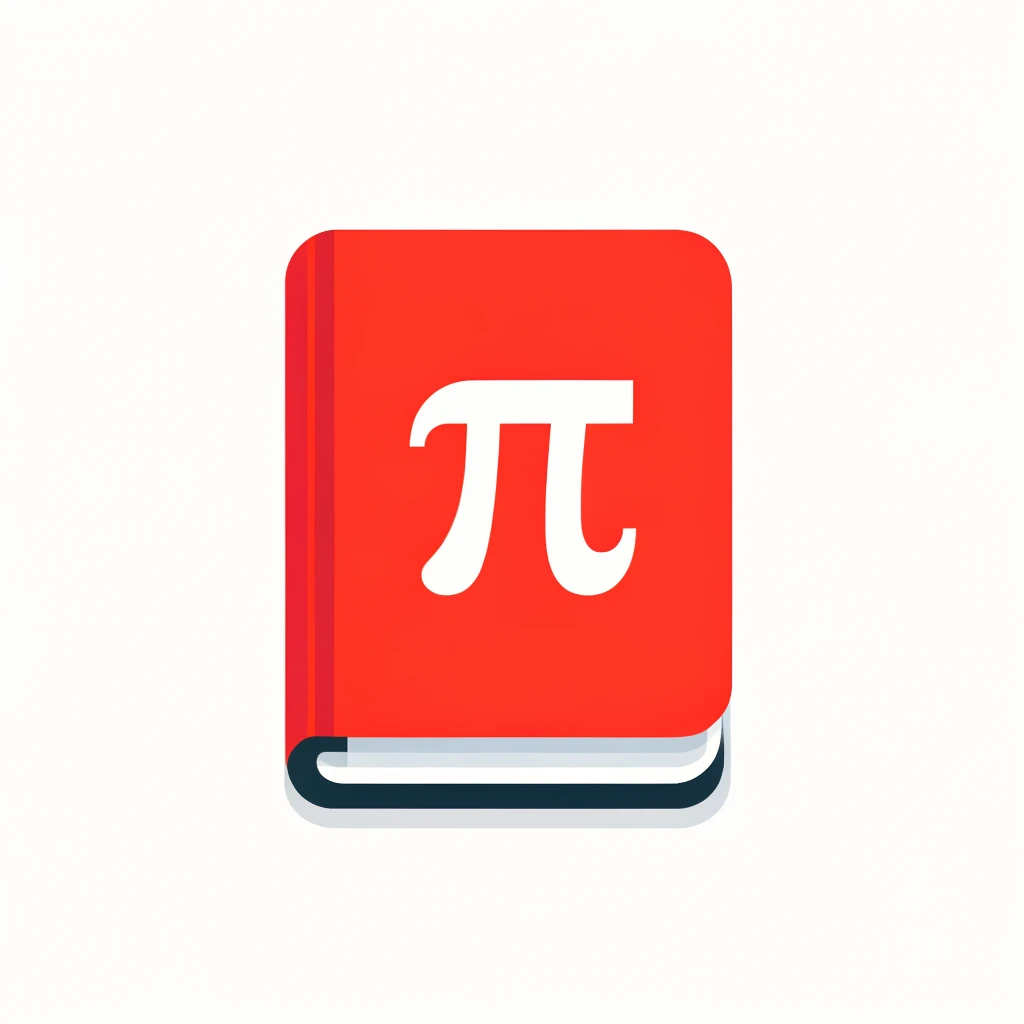


コメント